注釈
本文章における「仮想空間」は、「ソーシャルVRプラットフォーム」と「SNS(ソーシャルネットワークサービス)」の両者を指します。
この文章は僕の支離滅裂な文章です。
導入
私は一人のVRChatterとして、VRChatコモンズの文化の不健全性に触れることが多い。欲望・孤独・承認欲求など、人間の内面がいやでも見えてしまう。その原因は、「人間中心の設計を軸にしている仮想空間」にある。
私たちはモブではない――だからこそ
人間という生物は自己主張をしがちだ。そして自分を認められたいと感じている。
しかし、過度な自己主張は現実世界では上手くいかない。
原始的なむらでは、むらの協力関係から外されるリスクがある。むらで協力して衣食住を確保するため、それは致命的。
現代的な社会でも、周囲から奇異な目を向けられ、十二分に生きづらくなる。最悪の場合、直接危害を加えられる。
仮想空間性をもつサービス(SNSを含む)が登場して以来、私たちは自由に自己主張できるようになった。
現実世界のネットワークと分断させることによって、私たちは衣食住を侵されずに、自己主張することが可能になったのだ。自分の好きなものを公表し、そこでコミュニティも次々とできる。素晴らしい文化だと思う。
しかし、日々流れる情報の波に、日々刺激されるコンプレックスに、日々求める承認欲求に疲れてはないだろうか?
結局のところ、自己主張を封じられた世界にも、自己主張が中心の世界にも、人間は適応することができないのだ。
現在の仮想空間は現実の制約を離れ、自己主張が極めて容易な世界だろう。その表れがアバターだ。
現実のお金を使うことで、自分の癖が詰め込まれたアバターを作ることができ、多種多様なアバターが使われている。私のフレンドさんも、何万円もアバターに課金を行っている。この文化は自己主張中心型の世界の顕在例といえる。
潜在的には、自己主張に寛容な世界によって他人の欲望や感情が自分の領域に侵入してくる感覚を生む。自我の輪郭は曖昧になり、個の力は弱まる。流されやすい心は、孤独への耐性を失う。つながりが濃密であるほど、自己の輪郭を保つことは難しい。自由であるはずの仮想空間は、いつしか“他者の声に満ちた牢獄”へと変わっていく。
仮想空間は、原始の“共同体”とも、近代の“社会”とも異なる。
それは、無数の自我が衝突し、混じり合い、疲弊していく場所だ。
自己主張の自由が、人間を最も不自由にしている。
仮想空間で自然科学を見つけることはできない
自然科学とは、人間が自然という他者を観察し、そこから秩序を発見する営みである。
古来から現代まで、人間は人間社会と自然の調和のなかで暮らしてきた。しかし、仮想現実というものは自然と断絶しているとはっきり言える。なぜかというと、人間しかログインできないという、どうすることもできない問題があるからだ。
仮想空間上に哺乳類や昆虫、植物、微生物、細胞、地理、歴史、環境etc…がログインできるはずがない。また、それらが織りなす生物多様性社会やモノと光が織りなす自然の風景は仮想空間上に構築できない。仮想空間上で自然の風景を構築できていると思う人もいるだろうが、飽くまでそれは単純なプログラムとパーティクルで演出しているほかないのだ。
仮想現実で行える科学は、社会科学、形式科学、応用科学だろう。しかし、仮想現実で行うことのできない科学は自然科学だ。
仮想現実はいわゆる形式科学だ。自然ではなく、公理に基づくシミュレーションによって動く。つまり、モデルなのだ。モデルと本物にはかならず誤差があり、まだ見ぬ公理が隠れている。仮想現実は、モデル化する対象(物理現実)が大きすぎる故に、誤差やまだ見ぬ公理がとんでもなくある。そのシミュレーションの中に閉じこもっていると、それらの公理を感じることも、見つけることもできなくなる。人生において大きな学びの元となる自然と切り離してしまえば、人から学ぶことしかできず、ドツボにはまってしまうだろう。
現在、仮想現実は物理現実の拡張としての進化を遂げている。例えば、「物理法則から離れた新たな表現」や「空間性による親密なコミュニケーション」などなど。そんな流れの中、仮想現実を物理現実に寄せようとする動きはあまり歓迎されないだろう。まぁ、物理現実に寄せた仮想現実は、それこそ物理現実の劣化にしかならないので、役割分担するべきだと思うが。役割分担だからこそ、ワンサイドに閉じこもってはいけないと私は考える。
ちなみに私が一番伝えたかった項目…ボソ
人からものを学ぶ――宗教と同じ
人間は他者から学ぶ生き物である。言語も倫理も、他者との関係の中で獲得してきた。
だが仮想空間における学びは、極端に人間的なものに偏る。自然も死も不在の環境では、学びは“人間だけの閉じた循環”となる。この循環は自然を拒み、老廃物を排出する機会もない。結果として、特定のイデオロギーが肥大化しやすくなる。
VRChatにおけるイデオロギー闘争は、その典型例だろう。
「VRChatは現実の劣化論争」や「VRChatアバターサイズ論争」など、進展のない議論がしばしば繰り返される。
この原因は、人と人との「VRChatはこういう場所だ」というイデオロギー伝播による偏った学びの循環にある。
「VRChatらしい」そんな考えは頭の隅にないだろうか?私にもある。実際それらは、VRChatというコモンズに根付いたコミュニティの文化である。コミュニティの問題をコモンズの問題にしているから闘争が起きそうですが…まぁVRChatにおけるコモンズは内部システムだけで、ワールドを作っているのは私たちユーザーなので曖昧なものですが…
初心者案内がその最たる例ですね。(一応断っておきますが、初心者案内をしている人を批判しているわけではなく、人間にしか学ぶことができない状況を批判しているだけです。)イデオロギーに染まった人が案内をしてしまうと、そのイデオロギーが伝播する可能性が高い。
結局のところ人間同士、思想同士が争っても意味がない。自己主張や意見の衝突は、内部の循環を強化するだけで、真の理解や成長にはつながらない。
もしかしたら、喧嘩したいだけかもしれないけど…ボソ
人間だけの世界で学ぶことには限界がある。仮想空間の中で再生産される知識や価値は、必ず偏りを持つ。偏りを打破するためには、人間の外にある「他者」と接触する必要がある。自然、死、偶然、制約――人間を超える存在との出会いこそが、視点を拡張し、内向きな循環から解放する鍵となる。
つまり、仮想空間での学びは、人間中心の閉じた循環に留まるのではなく、外部の世界を媒介にして初めて完成するのだ。自然や現実から学ぶことで、自己の限界や偏りに気づき、真の自己成長の機会が得られる。
この点を忘れたまま、人間同士の争いに熱中することは、まるで「自分の影と戦っている」ようなものに過ぎない。
SNS性の欠点
SNS性とは、情報を“共有”し、“共感”によって結びつく構造そのものを指す。仮想空間も例外ではない。
この構造の核心は常時接続可能性にある。どこでも監視でき、いつでも監視され、いつでもどこでも会うことができる。利便性の極致だが、同時に深い依存を生む。
VRChatも「ソーシャルVRプラットフォーム」であり、SNS性を持つ。相手のステータスや、相手と同じワールドにいる他人に怯えれるのもSNS性があるからだ。SNS性が中心のVRChatで、オレンジステータスで位置情報を隠すという行為は多くの人に不安を与えているだろう。
かつて物理現実では、相手と離れている時間があった。そこには「相手のことを考える余地」があり、人はその静寂を“孤独”として受け入れることができた。孤独は、他者と距離をとりながら自己を整理するための時間でもあった。
しかし仮想現実では、常に接続された状態が前提となる。「いつでも会えるはずなのに、会ってくれない」という感情が生まれる。孤独は消え、かわりに“孤立”が生まれる。
他者とつながる自由は、他者に拒まれる恐怖へと転化する。
さらにSNS性は、投稿と反応のサイクルは短く、思索が定着する前に次の刺激がやってくる。思考よりも反射が先に働くようになる。
その結果、ユーザーは慢性的な精神的飢餓を抱え、他者の存在確認に依存するようになる。
仮想空間がこの構造を引き継いだとき、そこはもはや自由な交流の場ではない。
どこにいても、誰とでもつながれる世界は、裏を返せば「どこにいても、誰かに見られている世界」だ。孤独を失った人間は、他者との接続の中でしか自己を確認できなくなる。
そしてその自己は、いつでも更新され続ける“他者依存型の仮想人格”としてしか存在できない。
自然は仮想空間に実装できるのか?
技術的な問題と世論的な問題で実装は難しいだろう。世論的な問題は大きい。
自然というものは私たちに学びを与えるが、同時に試練を与える。その試練を好ましく思わない者や気力を削がれてしまった者が大勢いる以上実装は酷だ。
もし実装するとなると、SF小説の「セルフ・クラフト・ワールド」が似たような感じだったかな
。独自の進化を遂げた仮想現実を舞台にしてたし。
仮想空間との選択肢
仮想空間は「人間中心の夢」として作られてきた。風も、重力も、腐敗もない。だが、私たちが現実世界で学んできたのは、制約の中で生き、自然の中で作られる知恵である。風に抗い、雨に濡れ、思い通りにならない世界だからこそ、人は成長する。
仮想空間が閉じた遊園地である限り、人間は欲望を反射する鏡の中で循環するだけだ。
これからの私たちには二つの選択肢がある。
一つは、閉じた遊園地を開園させるか、
二つは、閉じた遊園地の外に出てみるかだ。
是非とも夢でない神秘を見てほしい。私は君たちとともに見てみたい。
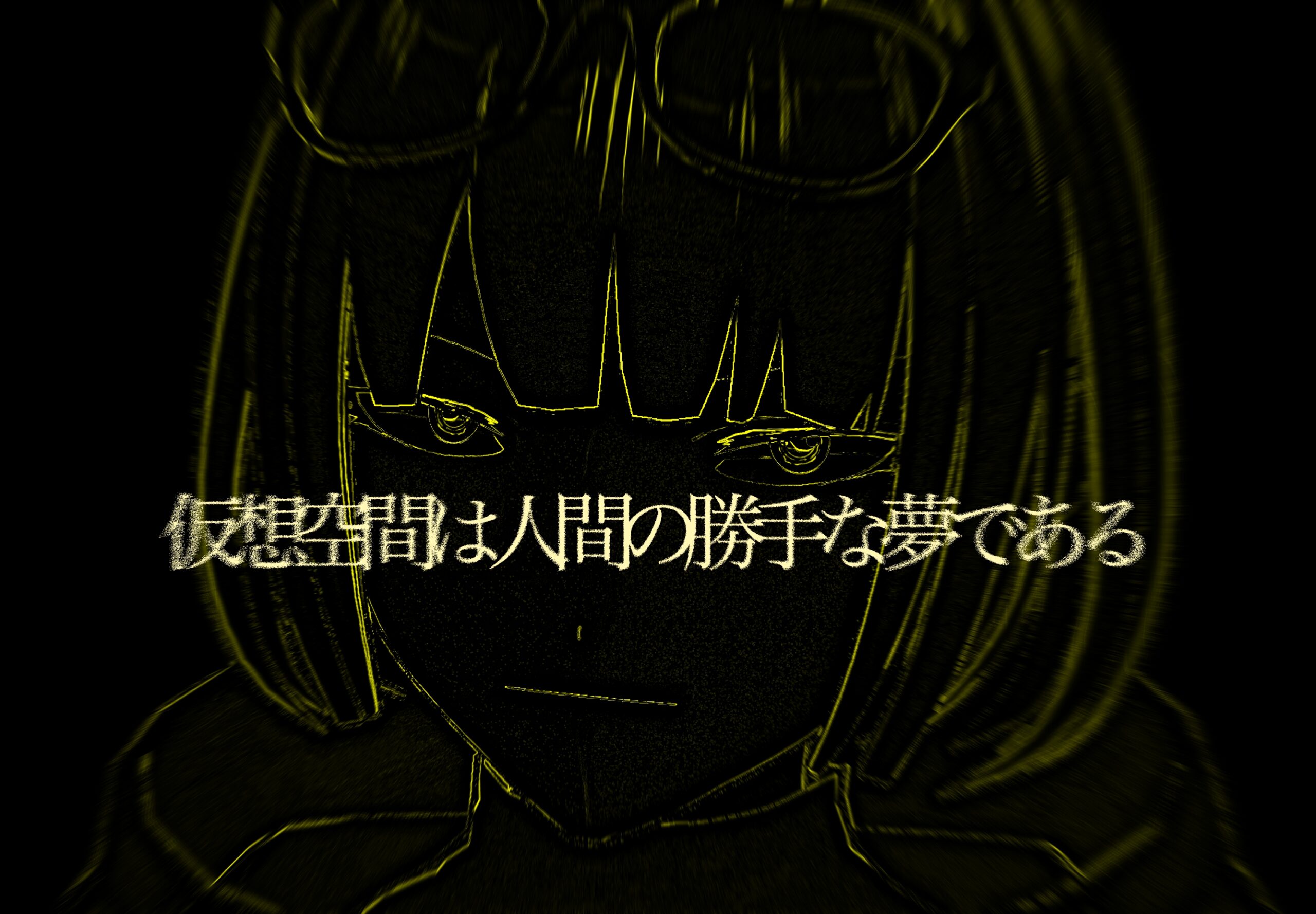


コメント